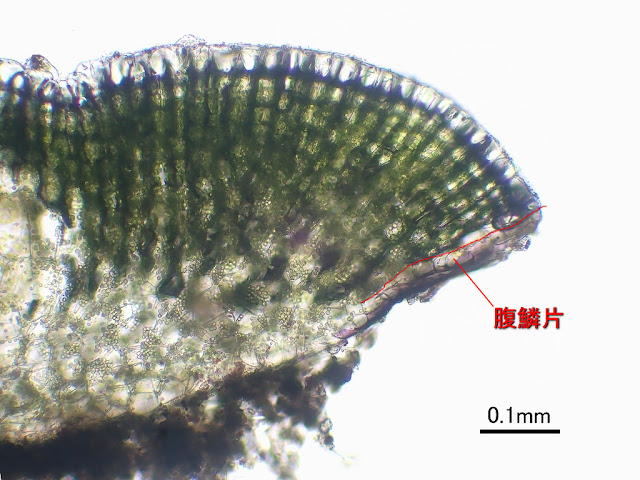10月に蓼科(標高約 2,300m)で撮ったフウリンゴケ Bartramiopsis lescurii です。 胞子は蒴口と口膜との隙間から出て、既に胞子散布は終了しているようです。 なお、こちらには7月下旬に撮影した、まだ蓋も帽もある蒴を載せています。
上は実際に生育している状況から、写真を 90°回転しています。 和名は上のようなイメージからでしょうか。
上の写真は、上が湿った状態で、下は乾いた状態です。 乾くと写真のように強く巻縮します。 葉の長さは、上の場合は葉鞘部を除いて 3.5mmほどです。
葉鞘部と葉身部との境付近には多細胞の長い毛があります(上の写真)。
葉縁には大きな鋸歯が並んでいます。
葉身細胞は方形~矩形で、長さは7~13μmです。
上は葉の横断面です。 薄板(ラメラ)は中肋上だけですが、葉身部は葉縁に近い一部を除いて2細胞層で細胞は縦に長く、ラメラとの連続性を感じます。